このほど、A4サイズ100ページ余の標記作品集が完成した。学芸員の全面協力を得て、構想からゴールまで約3ヶ月を要した。
刊行のそもそもの動機は、三浦綾子生誕100年を記念した田中綾館長執筆による小説『あたたかき日光-光世日記より』にあった。この新聞小説は2022年3月26日スタート!北海道新聞に毎週土曜日掲載。連載が楽しみであり、私は当該ページを毎回スクラップしてきた。小説の下部にはメモ(又は解説)欄があった。5月14日号には、綾子さんと「旭川市民文芸」の深いつながりが紹介されていた。
それによると、1964年「旭川市民文芸」6号あとがき~三浦綾子氏に寄稿を依頼したが多忙を理由に断られた。1965年同7号~インタビュー「三浦綾子さん訪問記」を経て、1966年同8号~綾子さんの本格的な寄稿が始まった。10年後の1975年には、「特集 作家・三浦綾子の世界」記事が組まれた。以下、標記作品集の心に残った事柄などを次に並べてみよう。
- 三浦綾子寄稿作品の数々
「日記抄」……“ハ指が痛い”“足がサイダーを飲んだよ”~いかにも、まことに、子供は詩人だ。“汝の敵を愛せよ”~小説『氷点』の前半のキーワード。
「N先生のこと」……白紙答案の裏に先生に対して幸福とは何かを問い質すと、“君の仕事は問題と向き合って、正解を見出すこと”と切り返された。綾子さんは科目の好悪がはっきりしており、嫌いな科目には身が入らず、ノートもとらず窓の外を眺めていた。
「赤子のような魂」……休学中に校則で禁止されていた喫茶店に、叔母や姉にくっついてはいるなど、好奇心旺盛な生徒であった。先生に見つかりひどくうろたえた。
「はなむけの言葉」……修学旅行の課題作文に奇抜な女学生入浴の図を取り上げた。自信作(?)特定の生徒の顔みて、授業すすめるのやめてと先生を批判した。
「気になる人」……早逝した超美人薬剤師とは親友になりそこねてしまった。残念!
- 特集 作家・三浦綾子の世界
山田昭夫氏「『石ころのうた』雑感」……『石ころのうた』と児童文学の傑作『二十四の瞳』を対比する試み。壺井栄氏に教師体験があったならどんな内容となったのか?戦争をどう捉えるのか?興味深いものがある。
佐藤喜一氏「三浦作品の聖女、俗女メモ」……各小説に登場する聖女、俗女の姿を大胆にナタを振るった。異論はないであろう。
後藤軒太郎(憲太郎)氏「作品と作家」……三浦綾子像=①人間が見える ②素材の吸収能力が高い ③イデアへの貢献度が高い ④才能を持つ許されを持つ、この分析は素人離れしている。素人というのは謙遜に過ぎない。
尾崎道子氏「心優しき代弁者」……各小説に登場する無償の愛の人として、次の各人を挙げた。『氷点』の陽子、『自我の構図』の雅子、『積木の箱』の和夫、『塩狩峠』の永野信夫、『道ありき』の前川正、『愛に遠くあれど』の三浦光世。構想3者実存3者。
高野斗志美氏「三浦綾子の文学世界」……氏は三浦綾子さんを、フランス詩人ランボオが唱える一匹の野兎と定めた。『氷点』はエゴの超克と実存の救済に尽きる。『続氷点』の“燃える流氷”はメタファー(隠喩)、視覚化されたメタファーである。“燃える流氷”は死と再生を意味している。
樋口清之氏「ガラシャは三浦さんの理想的人間像」……三浦綾子さんはガラシャを軸にして、ガラシャの心の動きを巧みに描き出すことに成功した。
- その他
谷口広志氏「三浦綾子さん訪問記」……対談記に自信はない。しかし、似顔絵には自信がある。全く谷口氏の言うとおりであった。
高野斗志美氏「『氷点』論」……原罪とは何か?『氷点』は大衆小説か〈戦後文学の変種〉か?「赤い花」の章で退院前日に自殺した正木次郎が登場する。生きる意味を失ってしまった次郎。正木次郎の死を知った啓造は、自分は何のために生きているのかと悩む。正木次郎に生きる力を与えることができなかったからだ。孤独であった。陽子もまた「愛」に飢えていた。
片山晴夫氏「三浦綾子『道ありき』に関する小稿」……“妻の如く想ふと吾を抱きくれし君よ君よ還り来よ天の国より”この歌は『道ありき』に収められた67首中最も秀逸な作品である。『道ありき』は著者の青春の記であり、女性の自立を問うた物語でもある。
三浦夫妻の終生の友人黒江勉氏は、名文を遺した。“『氷点』は既にして見えざるダイヤモンドダストとしてその兆しを宿していた”
異色の大作家三浦綾子さんは小説やエッセイのほか、絵本などを書き残したが、それとは別に北海道郷土誌「北の旅」、文芸誌「旭川市民文芸」、郷土誌「豊談」、火曜会誌「VITA」、井上靖「赤い実の洋燈」読書会報、各種写真集序文などへの寄稿が知られている。このように綾子さんの周辺雑事を調査・研究することも、私たち案内人の重要な役目だと思っている。「北の旅」寄稿作品集に続き、「旭川市民文芸」寄稿作品集が完成した。さて、次はどうするか目下思案中である。
by三浦文学案内人 森敏雄

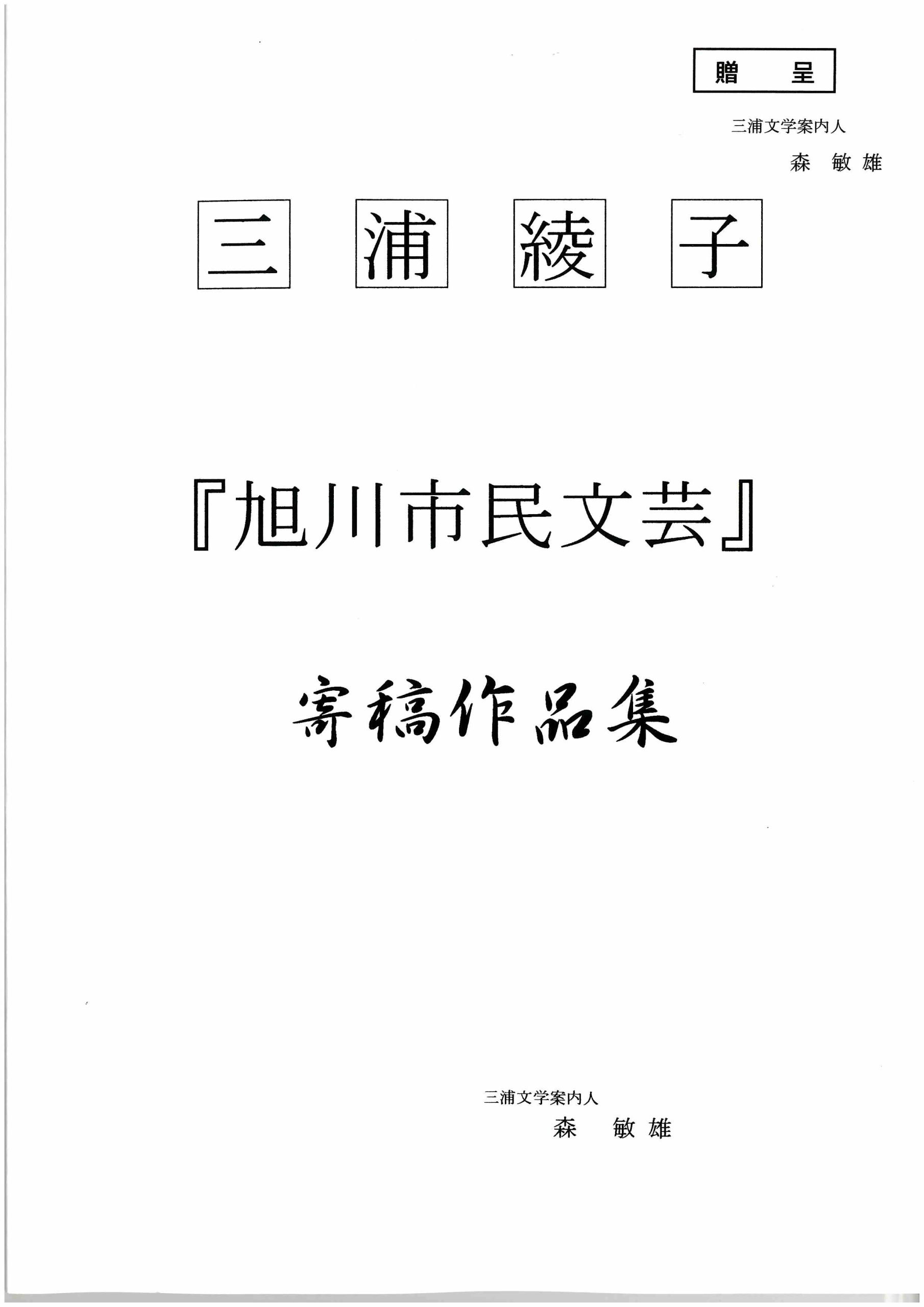

コメント